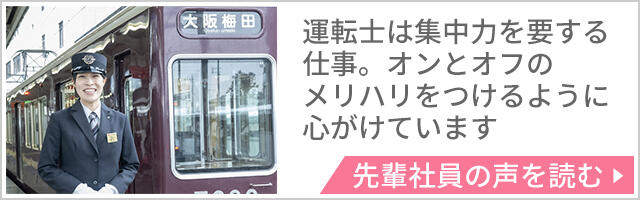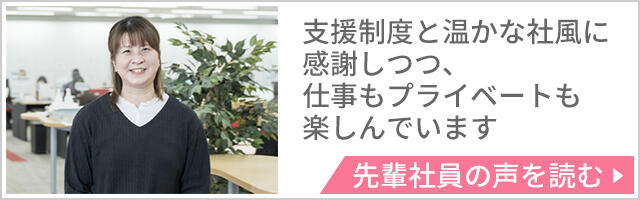女性活躍推進の取り組み
1. 社長メッセージ
阪急電鉄では、男女が共に活躍する組織の実現に向け、女性活躍を推進していきます。
2. 制度について
社員自身のキャリアや家庭の事情に合わせて利用内容を選択し、安心して仕事と育児を両立できるように、法定※を上回る基準で制度を拡充しています。(※法定とは、育児・介護休業法等、一般法令で定められた内容を指します。)
また、仕事と育児の両立含め、より柔軟な働き方を推進するため、当社独自制度も整備しています。
|
★法定超 ☆当社 独自 |
制度 | 概要 | |
|---|---|---|---|
|
妊
娠 ・ 出 産 ・ 育 児 休 職 中 |
☆ | マタニティ休暇(無給)・オプショナル休暇(有給) | ・妊娠による体調不良の場合に取得可 |
| 時間外労働・休日勤務・深夜勤務の免除 | |||
| ★ |
分娩休暇 (無給・出産手当金等支給) |
・出産予定日の最大7週間前から取得可 ・休暇中は出産手当金と当社独自の補填により給与水準のほぼ全額を補償 |
|
| ☆ | あかちゃん誕生育児参画休暇(有給) | ・最大5日間取得可(男性社員) | |
| ★ |
育児休職 (無給) |
・子が3歳に達するまで取得可 ・育児休業給付金は受給可(法定と同様) |
|
| ☆ | オプショナル休暇(有給) | ・育児休職として取得可(最大20日間) | |
|
復
職 後
勤
務 |
★ | 短縮勤務 |
・子が小学校4年生の始期に達するまで選択可* ・4時間・6時間・7時間勤務から選択可* |
| ☆ | フレックス勤務(短縮勤務社員含む) | ・始業時間・就業時間の柔軟な設定* | |
| 育児時間(1日2回30分) | ・子が1歳に達するまで取得可 | ||
| ★ | 所定外労働の免除・時間外労働の制限 | ・子が小学校4年生の始期に達するまで申請可 | |
| ★ | 深夜勤務の免除 | ・子が中学校就学の始期に達するまで申請可 | |
|
休
暇 |
☆ | 半日年休(20日分・年40回まで) | ・育児中社員を対象とした、半日年休の取得回数の上限引き上げ(通常は年休を6日分、年12回まで取得可)* |
| ☆ | オプショナル休暇(有給) | ・子の看病や健康診断等の付き添いのための休暇として取得可(最大20日間) | |
| ★ | 子の看護休暇(無給) |
・子の看病や健康診断等の付き添いのための休暇として半日単位で取得可* ・子が中学校就学の始期に達するまで取得可 |
|
|
両
立 支 援 ・ そ の 他 |
☆ | 保育支援手当 | ・1ヶ月につき最大2万円、子が3歳に達する日まで支給(適用要件あり) |
| ☆ | ベビーシッター利用補助 |
・月30時間(短縮勤務社員は月20時間)まで、利用料の一部を補助
・子が小学校4年生の始期に達するまで利用可 |
|
| ☆ | 育児クーポン(在宅保育サービス割引券) |
・1枚につき1回あたり2,200円割引
・子が小学校4年生の始期に達するまで利用可 |
|
| ☆ |
カフェテリアプランにおける育児支援金・
子女教育補助金 |
・育児支援金36,000円・子女教育補助金24,000円を選択可 | |
| そ の 他 |
出産育児一時金・付加給付 | ・健康保険組合から支給 | |
| 出産祝金・入学祝金 | ・共済会から支給 |
*一部の部署では業務特性上、異なる内容が適用される場合があります。
※記載には無い利用期限・適用要件等が別途設定されているものがあります。
3. 取り組み内容
阪急電鉄では、さらなる女性活躍推進を目指し各種取り組みを行っています。

取り組み具体事例
| 育児休職取得者向け復職支援セミナーの実施 |
|---|
| 育児休職取得者を対象に、育児と仕事の両立に向けた工夫やポイントを伝え物理的・心理的準備を促すと共に、復職に伴う不安を払拭することで、スムーズな復職と職場での活躍を支援しています。先輩社員との交流も行い、先輩社員や同世代の受講者との有意義な情報交換の場にもなっています。 |
| 育児休職取得中社員への定期的な情報提供 |
| 分娩休暇・育児休職取得中の社員に、月1回の「育活メール便」(職場からのメッセージや社報・社内誌等封入)の送付を行い、会社・職場の情報を定期的に伝えることで、安心かつスムーズな復職を支援しています。 |
| 上司向けマネジメントハンドブックの配布 |
| 仕事と妊娠・育児を両立する社員を部下に持つ上司向けに、部下とのコミュニケーションや職場マネジメントのポイントをまとめた「マネジメントハンドブック」を配布し、1人ひとりがより一層活躍する職場づくりを支援しています。 |
| 保育支援手当 |
| 出産・育児のために休職する社員の早期復職を支援することを目的として、復職後、子が3歳に達するまで1ヶ月あたり最大2万円の保育支援手当を支給します。この手当により、社員の仕事と育児の両立への意欲向上にもつながります。 |
| ベビーシッター利用補助制度・育児クーポン配布 |
| 勤務時間中にベビーシッターを利用した場合、利用料の一部を会社が補助しています。社員の費用負担を軽減し、業務の繁忙期や出張の時でも、育児の気がかり無く柔軟に業務に励むことができるよう支援しています。 |
| 育児休職の有給化 |
| 失効年休積立によるオプショナル休暇制度を整備しており、育児休職を最大20日間有給休暇として取得することができます。 |
| 週2回のノー残業デーの設定 |
| 週2回のノー残業デー(18:30完全退社)を設定しており、業務の生産性向上や社員の余暇の充実につながっています。また、その他の営業日においても、21:30までに完全退社するように啓発しています。(業務の特性上、ノー残業デーが適さない事業所・部署に対しては、別途生産性向上を啓発しています。) |
| 育児支援制度紹介リーフレット配布(年1回) |
| 全社員に対して、当社の育児支援制度をわかりやすく紹介するリーフレットを配布することで、仕事と妊娠・出産・育児を両立するために利用できる制度が充実していることを定期的に伝えています。 |
-

復職支援セミナー(託児付き)
-

上司向けマネジメント
ハンドブック -

育児・介護支援制度
紹介リーフレット
4. 女性の声
育児休職取得中社員への定期的な情報提供
育児休職取得中に、会社の情報や職場からのメッセージが月に1度送られてくるため、休職中でも職場の一員である意識を高く保つことができました。また、会社や職場の変化も定期的に知ることができるため、復職時も大きなブランクを感じませんでした。
ベビーシッター利用補助制度・育児クーポン利用
ベビーシッター利用料の自己負担がとても軽減されるため、本当に助かります。定期的にベビーシッターを利用しているので、子どもも慣れ親しんでおり、急な出張が入っても安心して仕事に励むことができます。
育児・介護支援制度 紹介リーフレット
多種多様な制度が1つの資料にわかりやすくまとまっていて、家族で一緒に見て育児計画を立てることができました。
 先輩社員の声
先輩社員の声
5. 現状について
人数
2021年4月1日現在(他社への出向者含む)
| 全体 | 男性 | 女性 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,356人 | 3,035人 | 321人 |
| 平均年齢 | 42.7歳 | 43.1歳 | 38.2歳 |
| 平均勤続 年数 |
21.9年 | 22.7年 | 14.2年 |
採用実績
| 全体 | 女性 | 女性比率 | |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 103人 | 14人 | 13.6% |
| 2020年 | 115人 | 18人 | 15.7% |
| 2021年 | 103人 | 18人 | 17.5% |
6. 関連リンク
行動計画
(阪急阪神ホールディングス株式会社・阪急電鉄株式会社・阪神電気鉄道株式会社)
女性の活躍を推進するため、次のとおり行動計画を策定する。
1.計画期間 2021年4月1日~2026年3月31日
2.当社の課題
- 管理職に占める女性労働者の割合が低い。
- 男性における職業生活と家庭生活との両立支援制度の利用率が低い。
3.目標
- 総合職の採用者に占める女性比率30%以上を継続する。
- 管理職に占める女性比率を着実に増加させる。(2025年度に5.5%以上を目指す)
- 総合職の男性育児休業取得率を向上させる。(2025年度までに男性育児休業取得率100%を目指す(※)) (※)女性育児休業取得率100%を前提とする。
4.取組内容
すべて2021年4月~
女性採用の積極化
- 各社ホームページにて、育児支援に関する会社の制度等の紹介内容を充実させる。
- 新卒採用媒体(ホームページ等)にて、女性労働者の活躍についての紹介内容を充実させる。
女性管理職比率の向上
- 育児と仕事の両立支援策を拡充する。
(会社の制度や手続きの周知、上司層の理解促進のためのパンフレット作成等) - 育児休職を取得した労働者のスムーズな復職を支援する。
(休職中の労働者への定期的な情報提供、復職支援セミナーの実施等)
男性育児休業取得率の向上
- 育児と仕事の両立支援策を拡充する。
(会社の制度や手続きの周知、上司層の理解促進のためのパンフレット掲載、総合職の配偶者分娩休暇拡充等) - 育児休職を取得した労働者のスムーズな復職を支援する。
(休職中の労働者への定期的な情報提供、復職支援セミナーの実施等)
女性の活躍の現状に関する情報公表
- 採用した労働者に占める女性の割合:総合職34.8%
- 管理職に占める女性労働者の割合:4.3%
- 総合職の育児休業取得率:(女性)100%、(男性)0%
(2020年3月31日時点)
くるみん認定

阪急電鉄は、2008年、2009年、2012年に大阪労働局よりくるみん認定を受けました。これは、次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画に定めた目標を達成し、
一定の基準を満たした企業に認められるものです。引き続き、次世代育成支援に向けた取り組みを検討していきます。

 遅延証明書
遅延証明書